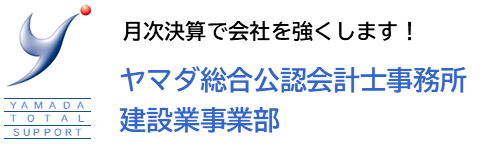近年、慢性的な人手不足や技能実習生の採用などにより、外国人社員を採用する会社が増えてきています。
今回は、外国人社員が退職に伴い母国に帰国する場合の注意点について会社が行う手続きを中心に見ていきたいと思います。
1.外国人社員が『居住者』か『非居住者』かで取り扱いが変わる
まず、前提として外国人社員が「居住者」か『非居住者』かで、取り扱いが変わります。
◯居住者→国内に住所を有し、現在まで引続き1年以上居所を有する個人
◯非居住者→『居住者』以外の個人
例えば、技能実習生等のうち、在留資格が1年未満の場合は、『非居住者』と判定されます。
今回は、『居住者』に該当する場合に絞って、税務と社会保険の取扱いをご説明いたします。
2.退職時の税務関係の注意点
1)給与に係る税金について
①所得税
外国人社員が帰国する際は、12月を待たずに年末調整を行います。
②住民税
住民税はその年の1/1に住所がある人に対して課税される為、年の中途で帰国する場合でも納税義務が発生します。
従って、帰国する場合は以下のいずれかの方法で納税を行う必要があります。
イ)退職時に支給する給与や退職金から、残りの住民税を一括して徴収する。
ロ)納税管理人を選任する
→日本から出国するまでの間に住民税を納める事ができない場合は、出国する前に、自身に代わり税金の手続きを
行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
2)退職金に係る税金について
外国人社員の退職時に退職金を支払う場合に注意すべき点は『退職日』がいつかという点です。
①退職日にはまだ出国していない場合
→日本人社員と同様に、退職所得控除が認められる通常の税金計算になります。
②有給消化などで退職日にすでに出国して、非居住者となっている場合
→非居住者に対する退職金の支払いとなる為、原則として支払額の20.42%を源泉徴収する必要があります。
3.退職時の社会保険関係の注意点
社会保険関係では、本人が脱退一時金の受給が受けられる可能性があります。
脱退一時金は、日本国籍のない社員にのみに認められる制度で、日本を出国した外国人社員に、それまでに支払った
厚生年金保険料が掛け捨てにならない様にという趣旨で支給されるものです。
請求期限は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内の為、忘れずに請求するよう退職者に周知する必要があります。
また、国によっては「社会保障協定」により母国の年金との年金加入期間の通算ができる場合もある為、脱退一時金の受給
を申請するのか、慎重に検討が必要です。
尚、脱退一時金は、税務上、非居住者に対する退職所得となりますので、上記2の2)②と同様に20.42%の源泉所得税徴収
の対象となります。